抗菌化学療法に興味のあるまたは従事している薬剤師の多くが目指す認定の一つに、
日本化学療法学会が認定する、抗菌化学療法認定薬剤師があります。
今回は、抗菌化学療法認定薬剤師を目指している方
これから認定を目指そうと思っている方
抗菌化学療法の知識と経験を積みたい方へ
そのような方に向けて、
今回は抗菌化学療法認定薬剤師取得のためのロードマップを紹介します。
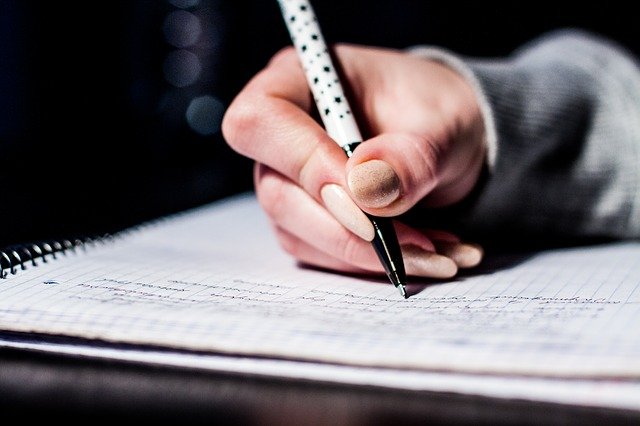
初めに
今回、作成しました抗菌化学療法認定薬剤師のロードマップをご覧いただく前に
自分の自己紹介です。
自分は5年前にこの抗菌化学療法認定薬剤師を1回で合格し取得済みです。
また、現在も取得を目指す後輩への指導を行っています。
そのため、現在も認定の取得、症例報告の作成について説明、指導ができると思います。

つまり、今回の記事もエアプレイ(机上論)でなく、
実際に取得、指導を基に作成しました。
今回の記事は全体像について紹介します。
特に不安のある症例報告については別記事での紹介を予定しています。
今後も最新情報にそって内容を更新する予定ではありますが、
更新日時をご確認の上ご覧ください。
どんな人におすすめ
この認定を取得するメリットについてですが、
認定を持っているから取れる算定や施設認定への条件にはなりません。

えっ!それなら何で目指したの?

自分は、感染症の勉強の過程で目指したのがきっかけだね。
感染専門チームにも入りたかったから、
その足掛かりになればと思ってたよ
自分が考える取得を目指す理由には以下のようなものが考えられます。
- 抗菌薬について勉強したい
- 抗菌薬について勉強していて実力をつけたい
- 部署内でICTなどのチームで活躍したい
- 将来は抗菌薬認定、専門薬剤師を目指したい
などでしょうか。
抗菌薬治療に興味がある、今後もこの分野で専門性を高めたい人におすすめの認定だと考えます。
また、認定取得までに培った
- 抗菌薬に関する知識
- 実際に症例に介入した実績
- 症例をまとめた経験
は自分の薬剤師人生にとって大きな財産になりました。
もちろん集積した症例は他の認定、専門の申請にも使えますので、
まずは、抗菌薬の症例報告を集めておいてから考えるのもありです。
なにより、感染症・抗菌薬について勉強すること、症例を集積することには何のリスクもありません。
認定要件について
まずは、認定要件を確認し取得までに必要なことを確認しましょう。
認定要件は日本化学療法学会のホームページを確認してみましょう。
認定の申請基準は以下の通りです。
抗菌化学療法認定薬剤師の申請は下記の各項を満たす者とする。
- 本邦における薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格及び抗菌化学療法の見識を備えている。
- 申請時に、薬剤師として抗菌化学療法に5年以上かかわっていることを示す所属する施設長又は感染対策委員長の証明が得られる。
- 申請時において、本学会の正会員である。
- 医療機関において、薬剤管理指導・TDM(治療薬物モニタリング)・DI(医薬品情報)などの業務を通じて感染症患者の治療(処方設計支援を含む)に自ら参加した15例以上の症例を報告できる。
- 本学会の抗菌薬適正使用生涯教育セミナー・認定委員会の指定する研修プログラムなどにおいて、別に定める単位数を取得している。

日病薬の認定や論文投稿、学会での発表歴は必要ないんだね。
少し安心したよ

そうだね、それじゃ必要な要件について一つ一つ見ていこうか
1:抗菌化学療法の見識を備えている
まずは薬剤師であることです。
ここは皆さんすでにクリア済みですね。
次に、抗菌薬に関する知識についてですが、
この認定取得までの過程でに
- 抗菌薬に関する知識
- 実際に症例に介入した実績
- 症例をまとめた経験
を身につけていくので初めは知識0でも大丈夫です。

自分もゼロベースからのスタートだったよ。
過程でしっかりと勉強していけば大丈夫。
2:「薬剤師として抗菌化学療法に5年以上かかわっている」
薬剤師免許を取ってから5年間臨床に従事する必要があります。
つまりこのロードマップは最短で5年かけて行います。

慌てなくても5年間も準備期間があるんですね。

5年間で他の要件を満たせるよう準備しておこう。
「1万時間の法則」をご存じですか?
1993年にアメリカの大学で心理学者のアンダース・エリクソン教授が発表した理論です。
ある分野のエキスパートになるには1万時間の練習・努力・勉強が必要だという理論です。
仮に5年間、毎日感染症について勉強と実践をしたとします。
1万時間を達成するのに必要な時間は約5時間です。
感染症に関する専門知識を身に着けるのには自分でもこれくらいは必要だと思います。
決して楽な道ではないと思います。
しかし、到達できれば、自身をもって医師に提案でき、
同僚や後輩の相談にのることができるようになります。

成果を得るためには相応の努力や苦労は必要ということですね。
3:本学会の正会員である
この認定を取得、維持するためにはこの学会の会員になる必要があります。
今回は時間的、金銭的なコストについても提示します。
時間的なコストは先ほど示した通り最短でも5年間です。
症例の集積に時間がかかればその分延長が必要です。
次に、金銭的なコストの一つに学会の年会費があります。
日本化学療法学会の年会費は9,000円です。
「申請時において、本学会の正会員」になる必要があります
金銭的コストを抑えるのであれば、申請時に会員になりましょう。

学会への参加や講習会に出るのに必要ないの?

大丈夫
会員でなくても学会や講習会には参加できるよ。
4:15例以上の症例を報告
ここが一番ネックになっている人もいると思います。
安心してください簡単です。とは言いません。
座学(勉強)のみでなく、実践経験(提案、介入)が必要です。
そのためにも抗菌薬についての考え方と使い方を学び、実際に提案していきましょう。
気を付けることは、「インプットに時間をかけすぎないこと」です。
インプット=勉強はもちろん大切です。
しかし、臨床においては「実際に得た知識を使い、治療に介入すること」の方が重要です。
学習した内容はその日から介入できるようにしましょう。

介入のポイントはブログでも紹介しているから参考にしてみてください。
抗菌薬の考え方について学びたい方にお勧めなのが、
岩田先生の名著「抗菌薬の考え方、使い方」です。
初心者が中級者、上級者を目指す上で必要な治療の基本となる考え方から
抗菌薬の各論について読みやすくまとまっています。
初めの1冊としてもおすすめです。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
症例については難しく考えすぎなくとも大丈夫です。
自分のブログで紹介している介入事例はいずれも症例報告として実際に提出または指導した
症例を基にしています。
症例介入案を見て、背景知識をつけ、後はどんどん介入していきましょう。
そして、介入した患者さんとその内容がわからなくならないように
電子カルテにフォルダーを作り、IDと内容をメモしておくと良いと思います。
詳しい症例の書き方については学会のHPにも記載してあります。
今後、別記事で紹介できればと思っています。
書き方のコツについては下の記事も参考になると思いますのでご参照ください。
5:必要単位数の取得
講習会などで必要単位=60単位を集める必要があります。

60単位!そんなの無理だよ。
取るのにどれだけかかるの

落ち着いて
大丈夫、勉強の過程で単位もとれるから
対象となる講習会、学会は以下のようになっています。
1.本学会が主催する抗菌薬適正使用に関連したプログラム
抗菌薬適正使用生涯教育セミナー1日コース=30単位、半日コース=15単位(必須)
または抗菌薬適正使用ビデオセミナーもしくはe-learningが20または30単位
本委員会が主催、開催するプログラム10単位(選択)
2.学術集会参加
本学会の主催する学術集会=日本化学療法学会の年会=5単位(必須)
本委員会の指定する関連学会の学術集会=日本TDM学会、日本医療薬学会=2単位(選択)
3.本学会以外が主催する抗菌薬適正使用に関連したプログラム
本委員会が指定するプログラム・認定学術集会=2 or 5単位(選択)
まずは、抗菌薬適正使用生涯教育セミナー(1日コース)の受講が必要です。
この受講で半分の30単位が得られます。
毎年6月くらいに開催されますので、4~5月にはお知らせがHPに出ます。
WEBでは人数制限はありませんが、会場開催の場合はすぐに埋まってしまうので、
お知らせを見逃さないようにカレンダーアプリに確認するように入れておきましょう。
この講習会の参加費は非会員では10,000円です。
会員は5,000円ですの後述しますが、学会員になっても年会費分取り戻せません。
また、時間は1時間のお昼休憩を挟んで1日です。
会場は東京国際フォーラムで行われます。
遠方で参加が難しい場合はe-learningの受講になります。この場合、20単位になります。
この講習会についてですが、初心者~中級者向けの内容です。
ただし、事前に代表的な抗菌薬の各論は頭に入れておいた方が良いと思います。
そのうえで講習会に参加すると基本的な使い方から実際に使用して例まで紹介してくれる
非常に有用な学習機会となります。
後で紹介しますが、2回以上出る価値は十分あります。
半日コース(15単位)は総論よりも各論よりな印象です。
自分が経験したことの無い疾患だとわからなくてついていけないかもしれません。
中級者以上向けだと思うので、初めは1日コースをお勧めします。
次に必須なのが日本化学療法学会への参加が必須です。5単位もらえます。
5年のうちに1回は参加が必要です。
コロナ禍ではオンライン開催もありますが、現地開催に戻る可能性もあります。
住んでいるところの近くで開催したときに参加してしまいましょう。
参加費は15,000円。こちらは学会員割引はありません。
コストのみを考えると、学会員になっても講習会の参加費が▲5,000円では元は取れません。
ここまでで35単位(e-learningでは25単位)残り25~35単位です。
最もおすすめなのは抗菌薬適正使用生涯教育セミナー(1日コース)に
もう一度参加することです(30単位)。
内容的にも勉強を始めたばかりの方向けの内容ですし、
毎年内容も異なるので、2回参加は十分価値があると思います。
また、医療薬学会年会に参加すれば2単位/年です。5年参加すれば10単位です。
医療薬学会は病院薬剤師であれば毎年参加をお勧めしたいので、不足分はこれで補いましょう。
以上で、必要な単位は足ります。
新規申請
ここまでできれば申請をしましょう。
HPでは以下の書類を準備が必要と記載されています。
- 抗菌化学療法認定薬剤師認定申請書(新規申請書式-1)
- 薬剤師免許の写し(裏書のある場合は、裏書も含む)
- 規定の単位取得証明書(施行細則3参照)(新規申請書式-2)
- 症例一覧15例分(新規申請書式-3)
- 推薦状(施設長または日本化学療法学会評議員)(新規申請書式-4)
- 抗菌化学療法に関わっていることの施設証明書(新規申請書式-5)
- 申請料(1万円)振込み控えの写し
1、5、6のひな形の書類はHPからダウンロードできます。
施設長の印鑑も必要ですので、施設にもよりますが2週間の猶予をもって準備しましょう。
なお、申請時点で1万円かかります。
認定試験
ここまでで書類審査があります。
症例に問題なければ大丈夫なはずです。
最後の難関、試験です。
これは過去問が公開されていないので頑張って勉強するしかありません。
しかし、ここまでの過程で抗菌薬と感染症について5年間勉強し、
実際に症例に介入して経験を積み
症例をまとめる段階でガイドライン等も確認しています。
実際に自分は専用のテキストを読んでいませんでした。

えっ!?なんで?

テキストの存在自体を知らなくてね(笑)
試験会場でみんな同じ本を読んでるのを見て
いやな汗をかいたのを覚えてるよ。
情報取集が不十分で痛い目を見る悪い例ですね(本当に落ちたと思いました。)。
学会より以下のテキストがHPで販売されています。
Amazonや本屋さんでは売っていないので、学会HPより購入するしか方法はありません。
※メルカリ等で使用済みであれば安く購入もできます。
ちなみにお値段は以下の通りです。
抗菌薬適正使用生涯教育テキスト(第3版):4,400円
抗菌化学療法認定薬剤師テキスト 改訂版2021:5,500円
後で内容を読んでみましたが、試験の出題内容がしっかり記載してありました。
読んで損することは無いと思いますし、教科書としても有用です。
抗菌薬は新薬や新情報があまり出ないので、購入タイミングも特に考えずに大丈夫です。
合格後にすること
晴れて試験に合格すると認定登録の手続きをして完了です。
認定料は20,000円です。
その後は5年ごとに更新が必要になります。
学会参加と講習会参加は必須、必要単位も60点必要です。
なお、この間は学会員でい続ける必要があります。
取得にかかるコスト
認定の取得に必要な過程は以上です。
ここでコストをまとめてみましょう。
必要年数は5年
必要費用は
学会年会費1年分:9,000円+講習会2回:10,000×2+学会参加費:15,000円
+申請費用:10,000円+認定料20,000円=74,000円です(書籍代、交通費は除く)。
更新には+年会費9000円×4年分=36,000円が追加されるので、1回の更新が最低11万円です。
費用については長期的には固定費となってしまうので、ライフステージに対して検討が必要です。
自身の業務内容やキャリアパスを考慮して更新については考えましょう。
まとめ
今回は抗菌化学療法認定薬剤師の取得までのロードマップについて紹介しました。
自分はこの認定を取得する過程で、3つの力を身に着けることができました。
- 抗菌薬に関する知識
- 実際に症例に介入した実績
- 症例をまとめた経験
この3つを手に入れられたことは大きな財産です。
認定についてはいずれも困難であると思いますが、
興味のある方は頑張って目指してみてください。
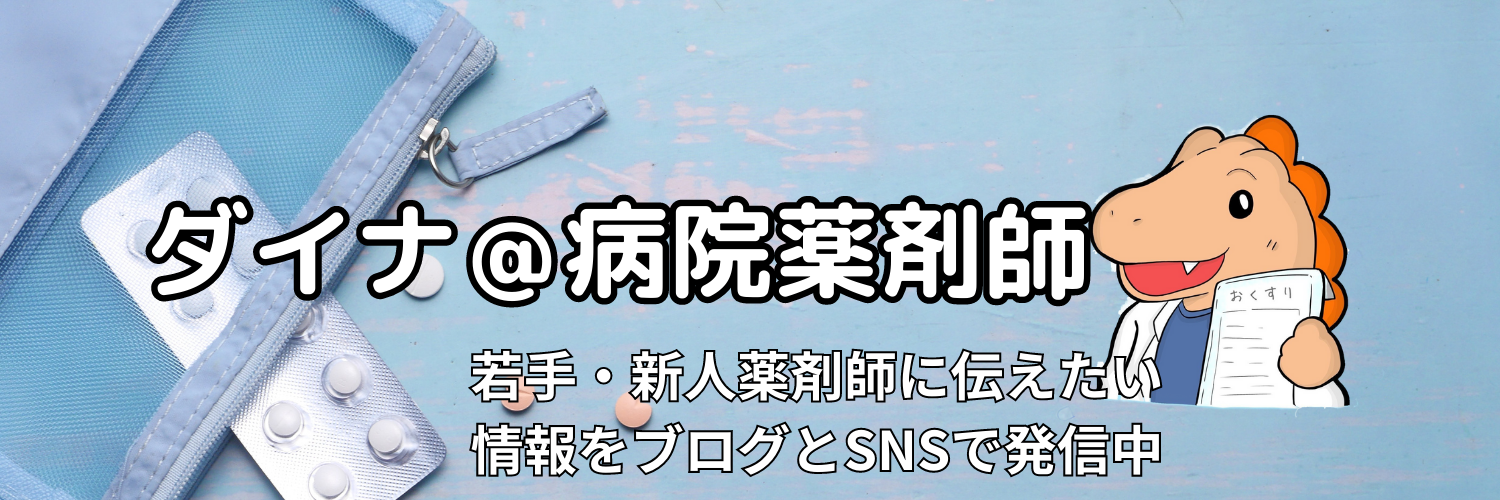





コメント